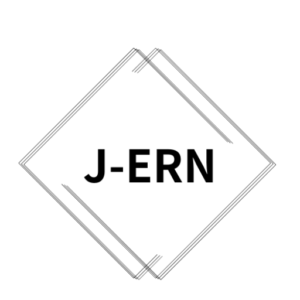教育系学会の多様性
教育という多面体と向き合う
教育系学会は様々な経緯で誕生する。科研費のプロジェクト、大学内の研究室や専攻、大学を超えた研究者間の勉強会、既存組織の分科会など、初めは小規模であっても、コミュニティが研究会に、そして学会へと発展していく。規模が大きくなると常設の事務局を設置し、一般社団法人、公益社団法人、特定非営利活動法人などの法人格を所有して安定した組織運営に力を入れるようになる。
学会は教育を捉えるための1つの枠組みであり、アプローチである。ご存じのとおり教育は様々な角度から切り込むことのできる多面体のような性質を持つ。教育研究の問題領域は実に広く、5W1Hの組み合わせから成る多様なテーマがあり、議論が尽きることはない。
教育の難しくそして面白いところの1つは、人類が誕生してから今日まで、何がよい教育なのかについて共通の見解が得られておらず、今なお追求し続けている点である。人類が経済活動や医療行為を始めるずっと昔から、教育や学習は始まり、ゆえに私たちは進化を遂げてきた。だが、科学が世界の真理や普遍的法則を見つけ、画期的な医療技術を開発してきたあいだに、教育研究は優れた発見をどれほどしてきただろうか。ICTやアクティブ・ラーニングや学び合いといった巷で流行っている手法や思想が「よい教育」だと自信をもっていえる人は、それほどいない。かと思えば、数十年、数百年前の考え方を持ち出してきてその素晴らしさを力説する者もいる。新しい時代に生まれるものが、必ずしもよいものとはかぎらないところに、科学と教育の決定的な違いがある。
よく耳にするのは、よい教育は子どもや学習者の数だけある、というものだ。道徳教育も金融教育も環境教育も情報教育も、どれも理念上大切であることは間違いないが、そのすべてを柔軟にこなせる全知全能の人間は存在しない。私たちの主義主張は、宗教と科学、言説(考えていること)と実践の間でつねに揺れ動いている。究極的にいって、その人にとってよい教育だったかどうかは、その人が一生を終えてからでしか検証することはできないようだ。
教育は全くもってとらえどころのない研究対象で、目的もはっきりと決まっているわけではないが、誰もが何らかの教育に従事した経験があり、誰もが教育を語ることができる。このようなアクセスの良さも教育研究の特徴であり、だからこそ問題がよりいっそう複雑になる。教育系学会はある種の閉鎖性という欠点もあるが、学会独自の学術的な観点から教育について議論できる重要なコミュニティである。そこでこの記事では、少しでも読者が学会に興味を持ってもらえるように、日本の教育系学会の特徴を紹介してみたい。
教育系学会の展開
J-ERNが収集している教育系学会の一覧データ(2023年9月3日時点)を用いて、各学会の設立年代を整理したのが下のグラフである。これは現在まで活動し、ウェブサイトを持つ学会のみのデータであり、J-ERNがまだ発見できていない学会がある点に注意してほしい。歴史の長い学会は「研究会」等の前身組織を起源としているが、最も歴史的な学会は1910年代に創設された。教育系学会の大部分は戦後に作られており、1950年代に学会結成の第一次ブームが訪れ、1990年代が設立の最盛期を迎えていた。その後、今日まで学会創設数は減少傾向にある。
まず興味深いのは、教育系学会の歴史はまだ100年も経っていないことだ。戦前にも研究会や勉強会と称する組織はきっとあっただろうが、現存する教育系学会がそれら組織文化を継承してきたという言及はまったくみられない。1940年代に入ってから学会や学会の前身組織が立ち上がった経緯には、いくつかの理由が考えられる。
1つは、大学の創設である。ほとんどの教育系学会は大学や大学関係者が発起人となっている。1950年には200しかなかった大学の数は、2020年には800にまで順調に増加し続けている。大学関係者が学会を組織し維持するための社会的環境の整備が進んだ結果、今日まで学会が存続し、継続しやすくなった。
2つ目は、科研費制度である。現在の科学研究費助成事業(通称、科研費)の制度が始まったのは1939年であり、1943年から支援対象が人文・社会科学系へと広がった。研究コミュニティを結成・強化したり、研究成果を対外的に発表したりする場所として学会が機能するようになった。
3つ目は、研究コミュニティの拡大である。これまでは大学の研究室や学科の中で、所属教員や在学生、卒業生、関係者が小さく狭い範囲の活動をしていた。しかし、研究上の限界を悟り、その発展を望んだこと、また非教育系学会が全国規模で活動するようになってきたことも受けて、共通コミュニティとしての学会を作り、全国を視野に入れた活動へと拡大していくこととなった。
4つ目は、戦前の学術統制から解放され、自由な研究風土が形成されていったことによる。これについては、日本教育学会の誕生を詳しく説明している川村・山本(1992)と寺﨑・中野(1991)の論文が参考になる。1941年に発足した日本教育学会だが、それよりも前の1936年に日本諸学振興委員会教育学会という文部省管轄の管制学会が存在していた。この日本諸学振興委員会教育学会の内部では、学術統制のもとに研究する学者と、自由な学問研究を好む学者との間に対立があったようだ。後者の人々が独自に集まり結成したのが日本教育学会であり、戦時下の学術統制のために作られた官立の学会から独立して、自由な研究と交流ができる民間の場が誕生することになった。このような戦後の自由な研究風土が学会創設の追い風になった。
川村肇・山本敏子(1992)「日本諸学振興委員会教育学会との対比における日本教育学会発足の意味」日本教育学会『教育学研究』第59巻第3号, pp. 263-270.
寺﨑昌男・中野光(1991)「日本教育学会小史」日本教育学会『教育学研究』第58巻第4号, pp. 299-309.
教育系学会の歴史はまだ日が浅いことに加えて、1990年代に学会設立の最盛期を迎えていたのも興味深い。その理由に確証は持てないが、30-40代のアクティブな若手・中堅研究者の人口と何か関係があるかもしれない。教育研究の限界と可能性の臨界点がみえてきた時期だったのかもしれない。この時代に創設された学会の誕生秘話を詳しくみていくことでその意味がきっと分かるだろうが、この記事では問題提起にとどめておこう。
1990年代を過ぎてからも、学会は今日まで創設され続けている。これには小さな派閥の争いや主義主張の食い違い、学会構成員の人間関係の問題もあるのだろう。もう少し事実に即して言及すると、2010年代からは、ESD、アクティブ・ラーニング、シティズンシップ、STEMなどの特定の概念にフォーカスした学会が次々と生まれていることは特筆すべきだ。これもまた、教育研究が新たなフェーズに入ったことを象徴する出来事なのかもしれない。こうした言葉に吸い寄せられる人は少なくないだろう。論文投稿数や会員数が減少し状況が芳しくない学会がある中で、このような振興学会は、従来の大学教員・学生だけではなく、様々なステーク・ホルダーをはじめとする一般市民、民間企業を巻き込みながらダイナミックな活動を繰り広げ、「学会が一部の人のためのもの」というステレオタイプを破壊しにかかっている。冒頭で「学会は教育を捉えるための1つの枠組みであり、アプローチ」だと述べたが、この傾向は概念研究のさらなる拡大によって今後ますます強まっていくだろう。教育に従事するすべての者はいずれ、どこかの学会に必ず1つは所属しているというような数奇な状況が起きても何ら不思議ではない。
学会が多様であることの意味
教育系学会を調べたことのある人なら感じたことがあるだろうが、分野が似通った名前の学会がいくつもある。国際理解教育学会と日本グローバル教育学会と日本ESD学会、日本教師教育学会と日本教師学学会、日本数学教育学会と数学教育学会と全国数学教育学会、日本科学教育学会と日本STEM学会…。説明しがたい大人の思惑があるのかもしれないが、小さな繭を作ることにいったいどんな意味があるのだろうか。「なぜ1つの学会で活動をしないのか」という単純な疑問が湧く。このような傾向には、教育研究が蛸壺化していくリスクはないのだろうか。また類似名称の学会のあいだに対立や上下関係は生まれないのだろうか。ここでは、「数学教育」と名のつく5つの学会、日本数学教育学会、数学教育学会、全国数学教育学会、東北数学教育学会、あきた数学教育学会を例に取り上げてみよう。
学会が多様である理由として、第1に、学会創設のルーツに違いがある。日本数学教育学会(https://www.sme.or.jp/about/history/)は1919年に「日本中等教育数学会」として創設された。1943年に「日本数学教育会」、1969年に今の「日本数学教育学会」へと改称された。詳細は日本数学教育学会が発行する『100年史』に記載されていると思うが、学会創設の経緯は次のようであった。
我が国の中等教育における数学に関しては研究の余地が少なくない。そこでその研究の方法を指導し材料を供給し結果を発表し互いに裨益を図る機関として全国数学教育関係者の団体を組織するというのがその主旨である。欧米諸国においてはこの種の機関の設立を見ないものは少ないありさまであるのに我が国では今日までこれを欠いていたのは数学教育の進歩を期するうえにおいて吾人の常に遺憾とするところであったが二百人有余の協議会出席者中一人の反対を唱えるものなく満場一致をもってこの動議を可決したのはもって時勢の要求するところを知ることができる。…(注:旧字体を読みやすいように書き換えている)
(日本中等教育数学会 1919,p.28)
先進的な欧米諸国に倣い、中等教育段階の数学教育研究を全国規模で推進することに第一の目的があったようだ。『日本中等教育数学会雑誌』の初期は、1つの完成された論文を掲載するというよりも、実践的で、通信的な意味が強く表れている(『日本中等教育数学会雑誌』の全巻はJ-Stageで公開されている)。もう1つ、興味深い特別会報を発見した。言論統制が厳しい戦前においても、学問の自由を保障する数少ないアクティブなコミュニティとして機能させようとしていたことが分かる。
本会雑誌は学術教育の施政の批判に渉りても差支えきように新聞紙法の手続き(保証金を納めて)をいたしてありますから、第三号よりこの種の投稿をも歓迎します(もとより過激にならざるように)。一般に活動的になってもらいたいのです。(注:旧字体を読みやすいように書き換えている)
(日本中等教育数学会 1919b,39)
日本中等教育数学会(1919a)「本会創立に関する経過報告」『日本中等教育数学会雑誌』第1巻1号,pp. 28-32. https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjsmet/1/1/1_28/_pdf/-char/ja
日本中等教育数学会(1919b)「特別会報」『日本中等教育数学会雑誌』第1巻2号,p. 39. https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjsmet/1/2/1_39_2/_pdf/-char/ja
数学教育学会(https://mes-j.or.jp/general/)は戦後の1959年に創設された。数学教育学会の『研究紀要』第1巻の「会報」をみるかぎり、より理論的・学術的な研究に重きを置いていたようである。この会報には、1958年に開催した2回の発起人会をおこない、(1)数学教育の心理学的研究(2)数学教育の社会的研究(3)数学教育史(4)数学史の教育的考察(5)数学教育の比較教育学的研究(6)教育内容の理論的研究(7)教授過程の理論的研究の7つの分科会が提案されていた(数学教育学会 1960,p. 75)。学会規約には、教育段階を問わず、数学教育学の研究を盛んにし、その普及にはかることが目的だと述べられている。
数学教育学会(1960)「会報」『数学教育学会:紀要』第1巻,p.75
全国数学教育学会(https://www.jasme-web.jp/)は1972年に「中国四国数学教育学会」として創設された。1983年に「西日本数学教育学会」、1995年に今の「全国数学教育学会」に名称が変わった。『数学教育学研究紀要』第1号に掲載されている論文の著者の大部分は広島大学の所属であり、英文雑誌名はHiroshima Journal of Mathematics Educationとされているように、広島の研究者が中心となり、徐々に活動の幅を広げていったようである。
このように、それぞれの学会は歴史的に独自のルーツをもって誕生し、当初の目的や活動範囲も異なっている。そして時代を経るごとに、学会の名称変更を見ても分かるように、この目的や活動範囲が徐々に重なりつつある。ただし、名称を変更したからといって学会のルーツや思想的背景が失われたわけではないだろう。ここを探ってみることは実に興味深いテーマである。
学会が多様である第2の理由には、上記と関連して、派閥や思想上の違いがある。この記事ではそこまではやらないが、数学教育系学会に所属している研究者をResearchmapで検索し、どの学会にどのような人々が単独で、あるいは重複して所属しているのかを調べればはっきりするだろう。
第3に、教育の地域性にこだわるという理由がある。上記にあげた全国規模の3つの学会のほかにも、「東北数学教育学会」と「あきた数学教育学会」というミクロな学会が存在する。東北や秋田における数学実践ならびに研究の独自的発展を強調すること、その地域で活動している特定の人々に強烈な影響を与えること、それぞれの地域が大切にしてきた数学教育文化を保存し継承すること、といったミクロな視点ならではのねらいがある。
第4に、活動の内容に幅がある。学会は年次研究大会のほかにも色々なことをしており、それぞれに特色がある。詳細は各学会の行事や学会事業を見れば分かるが、日本数学教育学会は地区大会も開かれるほど規模が大きく、『算数教育』『数学教育』『数学教育学論究』という複数の学会誌を発刊している。日本数学教育学会は「スタディーグループ」と呼ばれる専門研究会を設置し、学会員の参加を促している。全国数学教育学会は頻繁なイベント開催などはみられないが、英文雑誌の刊行に力を入れている。それぞれの学会でできることが違うところが、最適な学会を選ぶ1つの決め手になる。
まとめ
他分野の学会と違って、教育系学会は学会どうしの重なりが大きいところが、学会選びをますます難しくさせている。「尊敬している研究者や知り合いがいるからその学会に入る」という理由ももちろん重要であり、学会参加へのモチベーションや継続力にも関わるものである。そうした理由以外にも、各学会のルーツや活動内容が異なっているところも、学会の多様性が担保されている理由になっている。一概に規模の大きな学会が優れているともいえないし、規模が小さいからといって学会誌の査読が通りやすくなるわけでもないだろう。